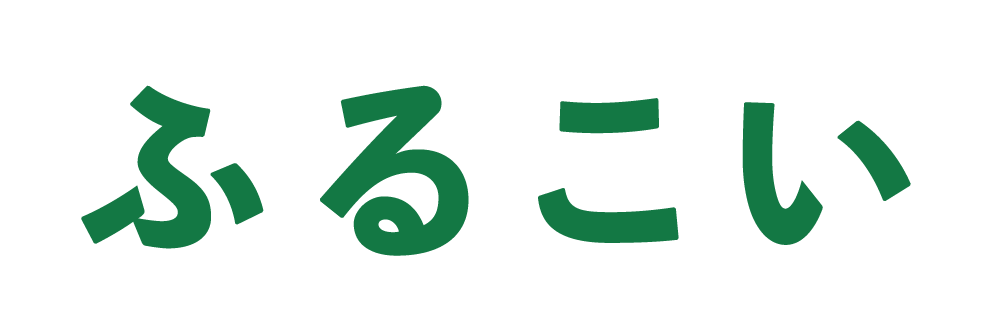総務省は「利用者に対しポイントを付与するサイトを通じて自治体が寄付を募ることを2025年10月から禁止する」などの制度改正を含めた、ふるさと納税制度のルール見直しを発表しました。
この記事ではルールの変更が今後のふるさと納税にどのような影響を与えるか、解説していきます。
- ふるさと納税仲介サイトポイント付与禁止の背景とは
- これからふるさと納税はどうなる?
- 2025年までにやっておきたい施策とは
- 結論:ふるさと納税ポイント付与禁止は改悪なのか?
ふるさと納税仲介サイトポイント付与禁止の背景とは
総務省の改正の背景
総務省は、ふるさと納税の趣旨に沿った運用を求めて度重なる通知や法改正を行ってきました。地場産品基準の中には、「寄付額のほぼ全額が税控除され、寄付額の3割相当の返礼品がもらえる」という高いインセンティブがすでに存在することが記されています。これに加えてポイント還元が行われており、特に年末などには30~40%のポイント還元キャンペーンが実施されることもありました。例えば、1万円の寄付で3000円相当の返礼品と3000円分のポイントバックが得られ、実質6000円分の特典を手にすることができます。これは本来の制度の趣旨から逸脱する恐れがあります。
本改正およびふるさと納税を通して、街をPRする「シティープロモーション」という本来の目的に立ち返るタイミングとして、いま一度施策をアップデートしていくことが求められてきます。
これからふるさと納税はどうなる?
毎年順調に利用者が伸長してきている「ふるさと納税」ですが、今回のポイント禁止の改正で「ふるさと納税」利用者が減るのではないかと考えている自治体・事業者も少なくないと思います。
改正後も、利用者の大幅な減少はないといえます。
本来、ふるさと納税は国民が応援したい自治体に寄付ができるだけでなく、寄付の使い道、すなわち税金の使い道を選べる制度ということ、また、返礼品のインセンティブは依然として高いため、全体の寄付額が縮小することはないでしょう。過去に制度が厳格化された際も同様の懸念がありましたが、ふるさと納税の金額や件数は例年増加し続けています。利用者の継続以降率は95%と高い数字を維持しています。
とはいえ今後はふるさと納税仲介サイトから流入してくる利用者が減ることも予想されるので、自治体もきちんと対策を行うところとそうでないところの差が出ることが予想されます。
2025年10月までにやっておきたい施策とは
2025年10月までの実施に向けて、事業者はふるさと納税に頼らない事業展開を再構築する必要があります。ポイント付与の禁止により返礼品のニーズが減少する可能性があり、特に返礼品を主要事業とする事業者には大きな影響を及ぼすかもしれません。しかし、返礼品のみを主事業とするのは健全な事業経営とは言えず、この機会に多角的な事業展開を模索することが重要です。
2025年10月までに間に合う具体的な施策をご紹介します。
データ分析による支援「ふるこい」徹底活用
ルール改正によって、広告宣伝も制限されるようになりました。今までのように広告代理店に頼らずに、各自治体や返礼品事業者が、独自でマーケティング活動をすることが必須となります。
「ふるこい」はふるさと納税で成果を出したい自治体と事業者のパートナーです。
「ふるこい」のデータを活用すれば、自身の自治体がどこに強いかを把握することができ、どの商品・サービスで勝負していくかを判断することに活用できます。また「ふるこい」で得られたデータをもとに豊富な実績を持つ専門家が組んだ戦略設計をもとに実際の施策実行までご支援します。
「ふるこい」を徹底活用して効率的に、適切なマーケティング活動を展開して早い段階から施策を準備し打っていくことを推奨します。
結論:ふるさと納税ポイント付与禁止は改悪なのか?
結論:ポータルサイト事業者には大きく影響を与えるものとなりますが、今回の改正は自治体や返礼品事業者にとって改悪ではなく「チャンス」と捉えるべきです。
自治体としてはふるさと納税仲介サイトに払う手数料が下がったり、広告費用が浮いたりするので、自治体が自由に使えるお金が増えるメリットがあります。しかしながら、その使える予算が増えた分、寄付額を伸ばすために各自マーケティング活動を強化した自治体にとっては、他の自治体と差をつけるチャンスとなりそうです。