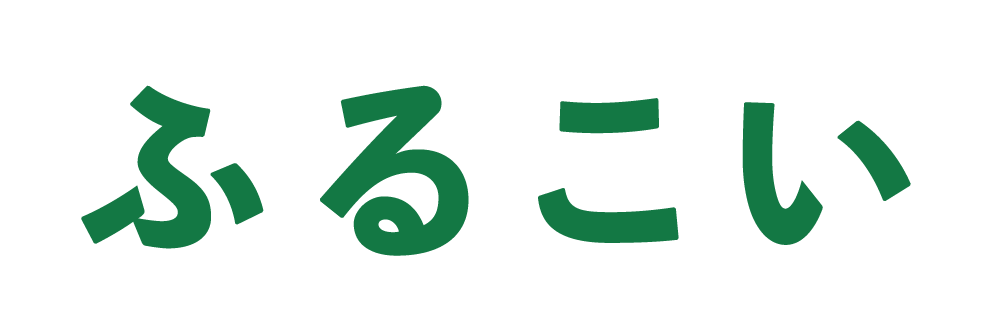ふるさと納税の適正運営を支える地場産品基準
ふるさと納税は、住んでいる自治体に納める住民税の一部を、ふるさとなど別の地域に振り分けられる仕組みです。そのため、寄附金の使い道には高い公益性が求められます。また、返礼品についても、地域の雇用を増やしたり、新たな地域資源を活用したりと、地域経済の活性化に役立つものであることが必要です。
返礼品を提供する際には、国が定めた「地場産品基準」に従うことが求められています。この基準では、総務省が「地域内で生産された商品や提供されるサービス」といった条件を設けています。この条件を満たすものが「地場産品」として認められます。
自治体は定期的に返礼品が基準を満たしているかを審査されており、総務省の承認を受けたものだけが返礼品として提供されます。このようにして、ふるさと納税制度の適正な運営が保たれています。
以下に、地場産品基準を示します。
第1号
「当該地方団体の区域内において生産されたものであること。」
地域内で生産された農産物などの一次産品を指しています。
地場産品基準に該当する例
- 地域内で生産された野菜
地場産品基準に該当しない例
- 他市区町村で生産され、地域内で販売されている野菜
第2号
「当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであること。」
原材料が「主要な部分」と認められるには、その原材料が加工品などの重量や付加価値の半分を超える割合を占めている必要があります。つまり、地域内で生産された原材料を大部分使用し、地域外で製造されたものが該当します。
地場産品基準に該当する例
- 地域内で収穫したトマトを100%使用して、地域外の工場で製造されたトマトジュース。
- 地域内で生産された牛乳を100%使い、地域外の工場で製造されたチーズ。
- 地域内で育てた米を100%使用して、地域外の蔵元で醸造された日本酒。
地場産品基準に該当しない例
- 製造に使用したリンゴのうち、地域内で生産されたものが1割程度しか含まれていないジュース。
- 地域内で製造された味噌を一部だけ使用し、地域外で加工した鍋スープ。
- 地域内で採れた砂糖を少量だけ使用した地域外製造のスイーツ。
第3号
「当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。」
製造や加工などの工程で付加価値を判断する基準は、原材料の価格に対して製品の売価が地域内で50%以上の付加価値を生んでいることです。また、食肉の熟成や玄米の精白が該当する場合、原材料も地域内で生産されている必要があります。
例えば、1,000円の売価に対して800円が地域内での加工による付加価値であれば、付加価値率は80%となり、地場産品基準を満たします。
地場産品基準に該当する例
- 地域外で生産された豚肉を使用し、地域内で味付け、調理、真空パック加工を施した豚肉の惣菜。
- 地域外で収穫された米を、地域内で精米し、ブランド化して販売した米製品。
- 地域外で漁獲された魚を地域内でフィレ加工(皮、骨、血合いの処理)し、パック詰めして販売した魚介加工品。
地場産品基準に該当しない例
- 地域外で調達したブロック肉を地域内で単に切断し、パック詰めしただけの精肉。
- 海外で製造されたラジオを地域内で検品のみ行い、そのまま販売した製品。
- 地域外で製造されたビールに地域内でオリジナルシールを貼り付けただけの製品。
第4号
「返礼品等を提供する市区町村の区域内において生産されたものであって、近隣の他の市区町村の区域内において生産されたものと混在したもの(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。)であること。」
地域から直接流通に乗せるのが難しい場合に限り該当します。単に、他の市町村で製造されたものと一緒に配送されている、または同じ事業者が別の市町村で生産しているだけでは基準を満たしません。
地場産品基準に該当する例
- 地域内で生産された米が、複数市町村を管轄するJAを通じて流通する際、他市町村の米と混合され「○○米」として出荷された場合(地域内生産分が明確である)。
- 地域内で肥育された豚肉が、近隣市町村を管轄する食肉処理場で加工され、流通構造上、他市町村で生産された肉と一部混在した場合。
- 地域内で生産された茶葉が、複数市町村を管轄するJAを通じて流通する際、近隣市町村の茶葉と混合されることが避けられない場合。
地場産品基準に該当しない例
- 地域内と地域外で生産されたアイスクリームが、全国チェーン店で区別なく取り扱われ、流通構造上の混在とは関係がない場合。
- 地域外で生産された果物が、地域内産と区別されずに一括販売されている場合(地域内生産分が不明確)。
- 地域外で製造されたパンが、地域内の配送業者によって運ばれるだけで、流通構造上の理由で混在が避けられないとは言えない場合。
第5号
「地方団体の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品等であることが明白なものであること。」
過去にその地域で生産されていたものや、今後その地域でアピールしようとしているもの、地域出身者に関連すること、または地域に事業所があることだけでは、この基準には該当しません。
地場産品基準に該当する例
- 地元のキャラクターをデザインしたキーホルダーやぬいぐるみ。
- 地元の風景や名所を写真にしたポストカード。
- 地元のスポーツチームのロゴ入りタオルやマフラー。
地場産品基準に該当しない例
- 地元で創業した会社が、製造を地域外で行った加工食品(例:地元の企業が他県で製造したジャム)。
- 過去に玩具の産地だった地域が、現在は他の地域で製造された玩具を販売している。
- 地元出身のパティシエが、他県の工場で製造したケーキやクッキー。
第6号
「前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等に附帯するものとを合わせて提供するものであって、当該返礼品等の価値が当該提供するものの価値全体の七割以上であること。」
「当該返礼品等に附帯する」とは、主に地場産品が提供され、他のものがその付随的な部分であることが社会通念上明確である場合に該当します。また、「当該返礼品等の価値が全体の7割以上である」とは、提供される品物全体の調達費用のうち、7割以上がその地場産品にかかる費用であることによって判断されます。
地場産品基準に該当する例
- 地域内で製造されたそば(2,000円相当)と地域外で製造されたそばつゆ(700円相当)のセット
- 地域内で生産された野菜の詰合せ(3,000円相当)と区域外で製造されたバーニャカウダソース(1,000円相当)のセット
- 地域内で製造された木製の食器(4,000円相当)と区域外で製造された布製のランチョンマット(1,000円相当)のセット
地場産品基準に該当しない例
- 地域内で製造されたビール(700円相当)と地域外で製造されたグラス(2,000円相当)のセット
- 地域外で生産された商品(例:地域外産のチョコレート)と地域のPR冊子をセットにしたもの
- 海外製タブレット端末(3,000円相当)に地域内を探索できるアプリを予めインストールしたもの
第7号
7の1「当該地方団体の区域内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が当該地方団体に相当程度関連性のあるものであること。」
⑦の「その他これに準ずるもの」とは、サービスの大部分が地域内で提供されるが、一部が地域外で提供される場合を指します。例えば、地域内で宿泊を伴う旅行券や旅行クーポンなどがこれに該当します。また、地域外で提供されるサービスであっても、その主要な部分が地域に関連している場合、地場産品として認められることがあります。
さらに、国は市内で使用できる食事券に関して、食事の提供が市内で行われることが重要であり、市内で提供できるかどうかを基準に判断する見解を示しています。そのため、市内にある全国チェーン店でも該当しますが、食事券は市内店舗内で食事する場合のみ使用でき、テイクアウトには使用できないとされています。
7の2「当該地方団体の区域内において地域のエネルギー源により発電された電気であること。」
地場産品基準に該当する例
- 地域内で宿泊を伴う旅行券や旅行クーポン。地域を訪れ、地域内で宿泊することが条件となる旅行券やクーポン。
- 地域内の飲食店で使用できる食事券。地域内の飲食店が提供する食事券で、店舗内で食事をする際に使用できるもの。
- 地域外のアンテナショップ内で提供される地域内産のメニュー。地域外にあるアンテナショップ内で、地域内で生産された野菜や肉をふんだんに使用した料理を提供する飲食スペース。
地場産品基準に該当しない例
- 宿泊や体験が伴わない航空券。地域を訪れるための航空券のみを提供する場合、宿泊や地域内での活動が含まれないため該当しません。
- 市外でも使用できる食事券。地域内の飲食店が提供する食事券が、市外にある店舗でも使用可能な場合、地場産品基準に該当しません。
- テイクアウトにも使用できる食事券。地域内の飲食店で提供される食事券が、店内での食事に限らず、テイクアウトにも使用できる場合、地場産品基準には該当しません。
第8号
「(イ)市区町村が近隣の他の市区町村と共同でこれらの市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを共通の返礼品等とするものであること。」
「近隣」の定義については、単に地理的に近いというだけでなく、経済的、社会的、文化的、または住民生活において密接なつながりがある市町村を指します。具体的に「近隣」と判断するかどうかは、関係する市町村がそれぞれの地域の状況に応じて判断します。
地場産品基準に該当する例
- 近隣の複数の市町村が協力して、地元の特産品を組み合わせた新しいセット商品を作り、共同で販売するもの。例えば、地元の野菜とお米、特産の調味料をセットにした返礼品。
- 近隣の市町村が共通の観光資源を活用し、地域の伝統や文化を表現する共同の旅行パッケージを提供するもの。例えば、地域ごとの歴史的な建造物や自然景観を巡るツアーをセットにした返礼品。
- 地域の農産物を生産する市町村が、協力してオリジナルの加工品を作り、複数の市町村がその商品を共通して返礼品として提供するもの。例えば、地域の果物を使ったジャムやジュースなどを、複数の市町村で共同で販売するケース。
地場産品基準に該当しない例
- 近隣の市町村の同意なしに、地域外で生産された県の伝統工芸品を返礼品として提供するもの。例えば、県外で作られた革製品を、地元の伝統工芸品として紹介して提供する場合。
- 近隣の市町村が関与していない、他の地域で生産された商品を無断で返礼品として提供するもの。例えば、県外の農産物や工芸品を使った返礼品が、地域外での生産に関与しない市町村で提供される場合。
- 市町村間で連携がなく、一方的に他の市町村の特産品を返礼品として提供する場合。例えば、他市で生産されたお米や野菜を、特産品として他の市町村が提供するケース。
「(ロ)都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村と連携し、当該連携する市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを当該都道府県及び当該市区町村の共通の返礼品等とするものであること。」
地場産品基準に該当する例
- 県内全域の特産物について、県が主導し、県内の全市町村と連携して、県全体の特産品として共通の返礼品として取り扱うもの。
- 県内の特定の圏域(歴史的、文化的に関連が深い地域など)において、複数の市町村が共通の特産品として取り扱うもののうち、現在は一部の市町村でのみ生産されているものを、県の支援のもとで共通の返礼品として取り扱うもの。
「(ハ)都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村において地域資源として相当程度認識されている物品及び当該市区町村を認定し、当該物品を当該市区町村がそれぞれ返礼品等とするものであること。」
地域資源として広く認識され、全国的にその価値が高く評価されている物品がある場合、それが地元の特産品として認められることがあります。こうした場合、その物品が地元資源として適切かどうかを判断する際には、単一の市町村の判断ではなく、都道府県が関与して、市町村間の意見をまとめた上で認定する必要があります。都道府県が認定した場合、複数の市町村がその物品を返礼品として扱うことができますが、すべての市町村が必ずその物品を提供する必要はありません。例えば、認定を受けた物品を取り扱う事業者が特定の市町村にのみ存在している場合でも、その市町村だけが返礼品として提供することが可能です。このように、柔軟な対応が可能な仕組みです。
第9号
「震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により甚大な被害を受けたことにより、その被害を受ける前に提供していた前各号のいずれかに該当する返礼品等を提供することができなくなった場合において、当該返礼品等を代替するものとして提供するものであること。」
災害により、地域の生産者が他地域に避難しているなどの状況が続き、返礼品の提供が不可能となった場合、寄付者に地域の特産物を思い出してもらうことや、返礼品の提供を通じて特産品の生産再開への支援を呼びかけることを目的として、提供できなくなった返礼品の代わりに他の地域の返礼品を提供することが考えられます。
「災害」の範囲については特に限定はありませんが、特産品の生産が一定期間以上続けられないほどの大きな被害が生じるようなケースが想定されます。
なお、被災地支援を目的としても、被災団体以外の団体が被災地域の特産品を提供する場合は、「類するもの」には該当しません。
第99号
「前各号のいずれかに該当する返礼品等とのみ交換させるために提供するものであること。(告示第5条柱書き)(例:○○pay商品券、△△Pay)」
地場産品基準に該当する例
- 地域内の宿泊や食事、土産物など、幅広い加盟施設で利用できるふるさと応援券。